これって「わがまま」?4つのシーンで考える子どもの「主体性」「わがまま」の違い
この記事は、2021.10.27公開の内容を最新化しております。

さくらさくみらいの保育でモットーとしている「子ども主体の保育」。保護者の皆さんも「子どもの主体性を大切に、いいところを伸ばしてあげたい」「子どものやりたい気持ちを大切にしてあげたい」そういう想いで毎日を過ごしていらっしゃるのではないでしょうか。
とはいえ、時間に追われる日々、分かってはいてもなかなかうまくできないし、「これってわがままを甘やかしているだけ?」と不安になることも…。
今回は、長くさくらさくみらいでも園長をしていた平井さんにこの永遠の命題「わがままと主体性」について、ヒントを聞いてきました!
目次
・シーン1 お散歩に行きたくない!
・シーン2 (ごはんの時に)○○残して良い?
・シーン3 お茶ではなくジュースを飲みたいと言ったら?
・シーン4 ガチャガチャの前でやりたいと言い出し泣き喚きはじめた
・まだまだ深い「主体性」…チャレンジは続きます!
シーン1 お散歩に行きたくない!
お出かけの時に子どもが「行きたくない」と座り込んで動かないような状況、みなさんも経験があるのではないでしょうか?親もきょうだいも準備万端。早く出発しないと、この後の予定にも影響が…焦る気持ち、無情にも進んでいく秒針、まったく立ち上がる気配のない子ども…
この子の「行きたくない」、主体性だと思いますか?わがままだと思いますか?
「行きたくない」という言葉だけ聞くとわがままと思ってしまうのですが、子どもの立場になって考える(=子ども主体、ですね)と、『自分で行かないという選択をしている』ので、わがままではないんです。
「行きたくない」と言っている子を尊重してあげたいところですが、「どうしても上の子を迎えに行かなきゃいけない」などの事情もありますよね。
なので、何とかあれやこれやの手練手管でお出かけに「行ってもらう」ように仕向けます。こんな時、どうすればいいんでしょう?

シーン2 (ごはんの時に)○○残して良い?
たっぷり遊んで、さぁお待ちかねのお昼ごはんの時間。
保育園でお昼を食べていると、ある子が「先生、〇〇残して良い?」と聞いてきました。栄養バランスのことを考えると偏りなく全部食べて欲しい…。
この子の「〇〇残して良い?」、主体性だと思いますか?わがままだと思いますか?
まずは「なんで?」と聞き出してみましょう。「お腹いっぱいだから」「〇〇は嫌いだから」と答えが返ってくるかもしれません。もしかしたら体調が悪くてあまり食べられないかもしれない。そうするとこれは、子どもたち自身の考えや意志選択があってのことなので「主体性」となります。平井さん、こんな時どうしたらいいんでしょう?

シーン3 お茶ではなくジュースを飲みたいと言ったら?
水分補給の時間、のどが渇いた子どもたちは提供されたお茶を一気に飲み干しました。でも、ある子は「お茶を飲みたくない」と言い出します。お茶を飲まずにジュースを飲みたがる子もいるかと思います。
子どもの体内の水分量の割合は大人に比べ多く、体温調節機能が未熟なため水分のバランスを保つことが難しいと言われています。また、ジュースには糖分がたっぷり。大人としては、体のことを考えお茶を飲んで欲しい気持ち…。
この子の「お茶を飲みたくない」「ジュースを飲みたい」って主体性だと思いますか?わがままだと思いますか?

でも、「お茶は飲みたくないけどジュースは飲みたい」のような、“こっちは嫌だけど、こっちは良い”って…平井さん、これはさすがに「わがまま」だよね?

シーン4 ガチャガチャの前でやりたいと言い出し泣き喚きはじめた
それでは、最後にこのような場合はいかがでしょうか。
子どもとお出かけし、ガチャガチャの目の前を通った時、「お母さん、これ(ガチャガチャ)やりたい!」とねだられました。皆さんならどうしますか?
久々の外出だし、特に高いものではないし…たまにはいいかな。と、子どもにお金を渡しガチャガチャをする方も多いのではないでしょうか。
では、次に行った時もその次も「(ガチャガチャ)やりたい!」と言い出し、子どもがその場で寝転んで泣き喚きはじめた。ギャーっといきなり店内に響き渡る怪獣のような泣き声。周囲も驚き白い目でこちらを見ている(ように感じる)。一刻も早くこの状況をどうにかしなきゃと焦る心…思わず出そうになる一言、「わがまま言わないの!」。
この子の“ガチャガチャをやりたいから泣き喚く”というのは、主体性だと思いますか?わがままだと思いますか?

では、泣き止まない状況のとき、一体どのように対応すればよいのでしょうか。

まだまだ深い「主体性」…チャレンジは続きます!
ここまで4つのシーンを例に「主体性」と「わがまま」の違いのヒントを見てきましたが、子どもに事情があれば何でも「主体性」になってしまうような…。でも、そうして子どもの要望・欲求をすべて聞いていたら、将来どうなっちゃうんだろうと不安になりますよね。
その子のリクエストを1から100まですべて聞くこと、これは実は子ども自身が考えて、思考を巡らせて行動するという機会を奪ってしまうことになりかねないんだそうです。

保育園でも、主体性とわがままの違いに対して頭を悩ませている新入社員に対して平井さんは「答えを出すわけではないので、難しく考えなくて良いですよ」と言っていました。
「考え出すとみんな頭がはげそうになって、最後には少し薄くなってるの(笑)」。保育のベテラン園長でも悩む「主体性」と「わがまま」。まだまだ奥が深そうです。
今回の「主体性」と「わがまま」を始め、さくらさくみらいでは日々の保育の中で「どうしよう?」と悩んだことを共有し、みんなで解決策を話し合う研修を定期的に行っています。
皆さんも、ちょっと子育てに悩んだとき、ぜひ気軽に声をかけてくださいね!
さくらさくみらいの保育に興味を持たれた方は……
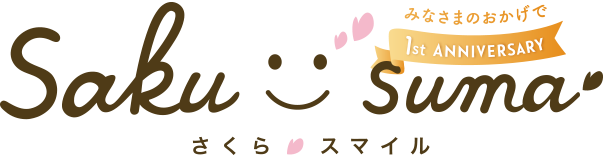

寒い冬を乗り越えよう!今が旬、冬の野菜を使った食育活動-720x550.png)

秋の味覚を楽しもう!-さつまいも掘りに行ってきました-720x550.png)
地域交流-800x550.jpg)
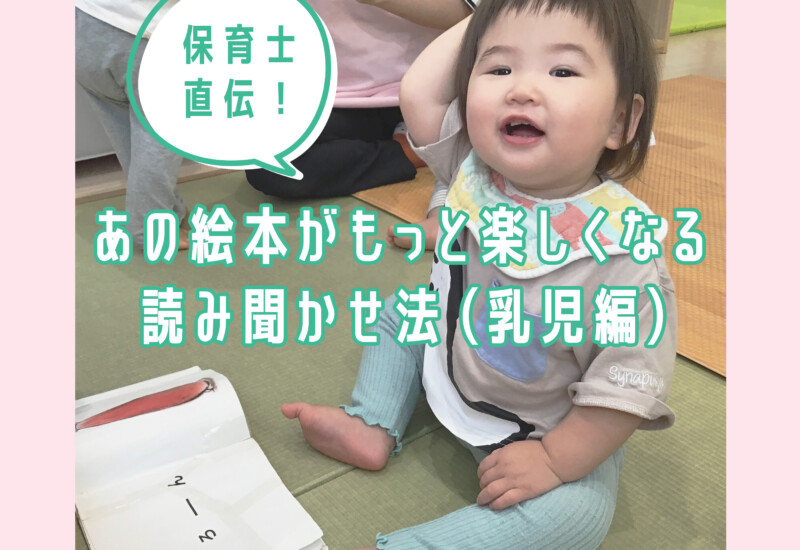

みんなの保育指針制作ストーリー-800x550.jpg)
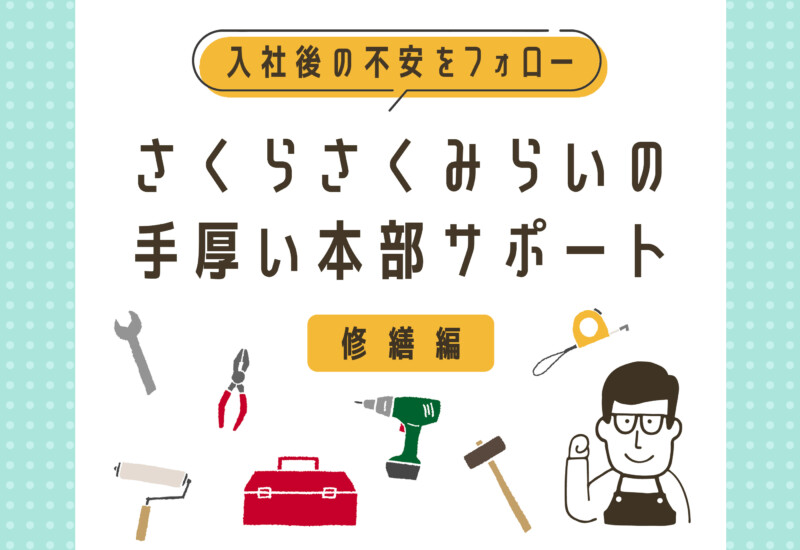
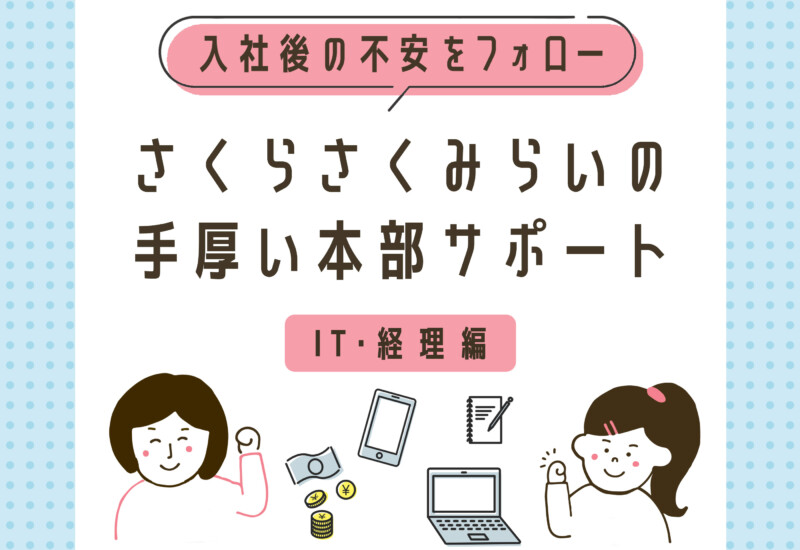
さくらさくみらいのサポート体制(新卒)-800x550.jpg)

七夕2-800x550.jpg)
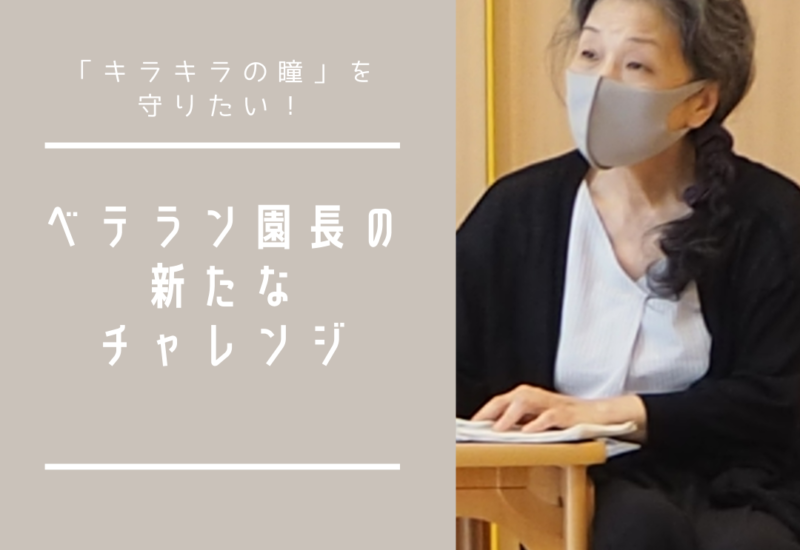
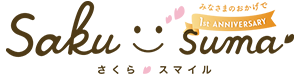
寒い冬を乗り越えよう!今が旬、冬の野菜を使った食育活動-500x500.png)
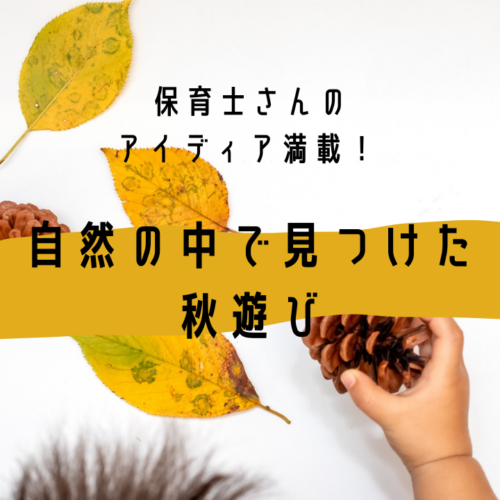
秋の味覚を楽しもう!-さつまいも掘りに行ってきました-500x500.png)
地域交流-500x500.jpg)